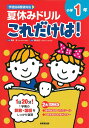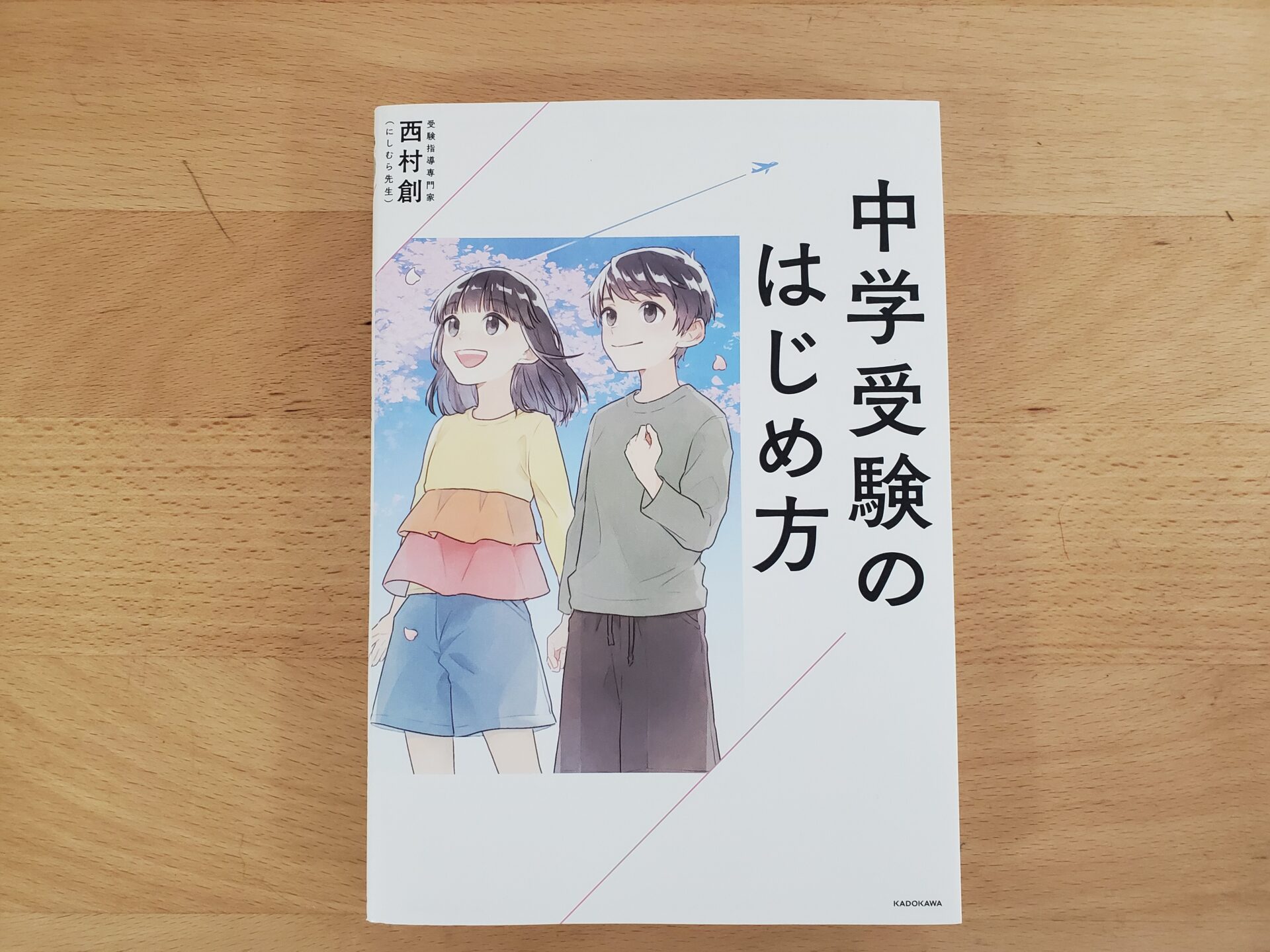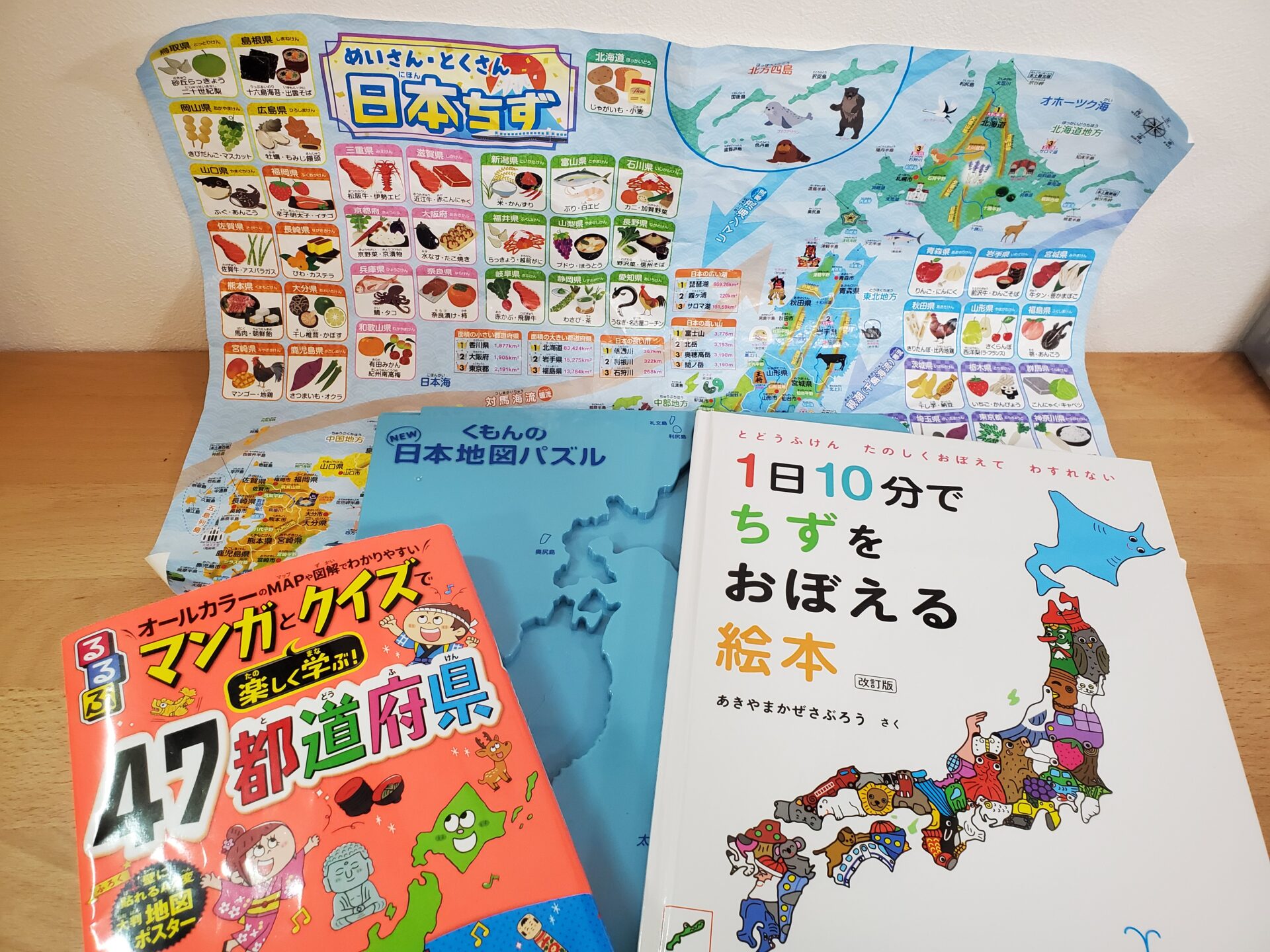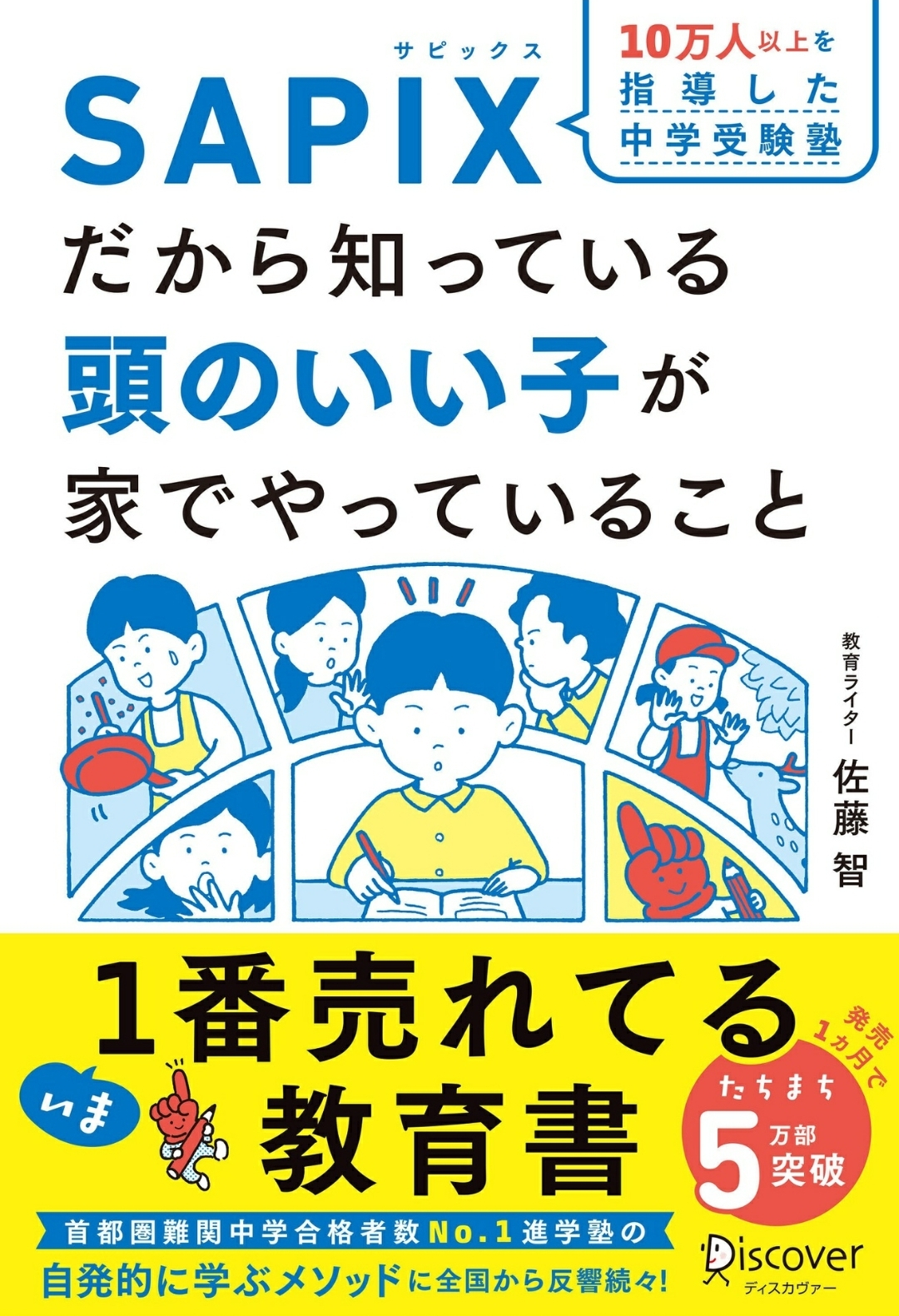【小1】夏休みの学童でやるドリル、おすすめ5選!

こんにちは!関西の中学受験ブログのマグロです。
中学受験に挑戦する小4の長女(エビちゃん)と小1の長男(サーモンくん)がいます。
本日は、小学1年生の夏休みに学童で取り組む、おすすめの市販のドリルを紹介します。

学童では毎日勉強タイムがあったよ!

ちなみに、我が家はおすすめしているドリルを全部やりました!
我が家の実体験に基づいたおすすめです!
夏休みの学童に、どの学習グッズを持って行くか問題

小学1年生の夏休み、学童にはどの勉強グッズを持って行けば良いの?
このように悩まれている親御さん、多いと思います。
特に、小学1年生だと夏休みの宿題が少ないので、宿題を終えた後に何をするのか。。。悩まれている家庭も多いでしょう。

例に漏れず我が家も、サーモンくんが3日で学校の宿題を終えてしまったので、追加のドリルを探すのに苦労しました。
我が家の経験から、小学1年生の夏休みに取り組むのにおすすめのドリルを紹介しますので、ぜひ参考にして頂ければと思います。
難易度が高すぎるドリルは良く無い

学童に持って行くようのドリル、難易度はどのように選んだら良いの?

学童では、勉強に一人で取り組むのが前提なので、高難易度はおすすめしません!
せっかく勉強させるのならば、よりレベルの高いものに取り組んでレベルアップを。。。と思ってしまう親御さんもいると思います。
しかし、学童で取り組むドリルは、「簡単〜普通」くらいのドリルをおすすめします。

自宅や塾と違って、教える大人がいないので、小学1年生の自分一人で取り組める難易度がおすすめです。
学童で行う勉強は、「新しい知識を身につけてレベルアップする」ための勉強ではなく、「学習習慣をつける」「デキる!を体験して勉強を好きになる」ための勉強と割り切るのが良いでしょう。

小学1年生で勉強がキライになってしまっては、困りますからね。
小1の夏休みにおすすめのドリル5選!

それでは、小1の夏休みにおすすめのドリルを、特徴と一緒に紹介します!
おすすめ度を★5段階評価で表していますので、参考にしてください。
① 大盛り!夏休みドリル 小学1年生
おすすめ度★★★★★
スイカの画像が目を引く、例年多くの小学1年生が取り組んでいる、定番のドリルです。

「ど」定番ではありますが、こちらを選択しておけば、まず間違いは無いです!
64ページとボリュームが多く、これ一冊で長持ちします。
難易度の設定も適切で、子ども1人で無理なく進めていける難易度です。
迷ったら、まずは「大盛り!夏休みドリル」に取り組み、取り組んでいる間に次のドリルを選択するのが良いでしょう。
② 学研の夏休みドリル 小学1年
おすすめ度★★★★★
大手学習塾である学研が提供している、小学1年生の夏休み向けのドリルです。
くもんのドリルもありますが、くもんより学研の方が「思考力系」の問題が多く、個人的にはおすすめです。
→大手のノウハウが凝縮された、小1の夏休みドリルになっています!
③ 算数と国語を同時に伸ばすパズル 考える力試行錯誤する力が身につく 入門編
おすすめ度★★★★☆
タイトルに国語と算数を同時に伸ばすとありますが、いわゆる「論理力」をつけるドリルです。

①②とは系統が違うのですが、こちらもおすすめです!
計算などの反射的な適応力ではなく、中学受験等に向けて考える力を鍛えたい場合は、このドリルに取り組むと良いでしょう。

入門編の難易度は、小1でも十分に解けるレベルです!

実際に僕も1人で解けたよ!
④ 夏休みドリル これだけは! 小学1年
おすすめ度★★★☆☆
ハードルを大きく下げて、まずはやる気を醸成するところからスタートしたい家庭には、「夏休みドリル これだけは!」をおすすめします。

ドリルのタイトルにもあるように、本当に「最低限これだけは!」という内容です!
正直、小学1年生ならば、楽しく勉強していればOKだと私は考えています。
学習塾等に通っている子には物足りない内容だとは思いますので、その点については注意が必要です。
⑤ 夏休みドリル マインクラフト さんすう・こくご・えいご 小学1年
おすすめ度★★★☆☆
マインクラフト(プレイヤーが自由にブロックを配置し、様々な構造物や世界を作るゲーム)を題材にしたドリルです。

マインクラフトが好きじゃないと、これを選ぶ理由はありません。笑

マインクラフトが好きな僕は、やる気MAXで取り組んだよ!
マインクラフト自体も、空間能力や思考力を鍛えるためにおすすめです。
最後に
小学1年生の夏休みに学童で取り組む、おすすめのドリルを紹介しましたが、別に夏休みだけではなく、小学1年生1学期の復習にはピッタリのものばかりです。

ドリルは腐るものではないですし、2学期に入ってからでも復習に利用することをおすすめします!
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!